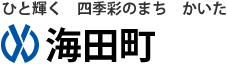海田町(カイタチョウ)名誉町民 織田 幹雄(オダ ミキオ)氏をたどる
第2回 父・織田 幹雄(オダ ミキオ)を語る(後編)
長男 織田 正雄(オダ マサオ)さん
現在「ふるさと館」で織田 幹雄(オダ ミキオ)の遺品の整理を行なっておられますが、出場した欧州やアジアでの国際競技会から父が持ち帰った膨大な資料は恐らく世界で日本にしか残っていないだろうと思われる貴重なものばかりです。
未整理の父の遺品には欧州遠征での買い物のレシートや洗濯の受け取り票、更に東京からレニングラードまでの日本国鉄のキップ、パスポートなどが膨大に残っています。
父の子供への教育方針を私たちは子供時代には認識していませんでしたが、大きくなってから、父には一貫した教育方針があったのを知りました。親子対話はあまりなく、父は無口でしたが、一貫した方針を貫いていたのでした。
父は私が中学生の頃、自分で作った小さな壺を弟と私に土産と言って渡しました。私の壺には「世界人と成るべし」、弟の和雄(カズオ)の壺には「先頭を切る者の偉大さを思え」と書かれていました。
私がこの意味を正しく理解したのはずっとあとのことです。
父は第二次世界大戦が終わってすぐ、富山県の私の学童集団疎開先に岡倉 天心(オカクラ テンシン)の英語の教科書を「これからは英語だ」と書いて送ってきました。
父の方針に同感であった母は夏休みにアメリカ人の家庭に入って英語を学べ、夜間学校でタイプライターを習え、アジアからの留学生を一日里親するから正雄(マサオ)が通訳しろ、また父はアメリカ人にアメリカ生活を教えてもらって来い、など今から考えると指導は一貫していました。
私がスタンフォード大学に留学した時、何故か初日に父が大学を案内してくれました。父は1932年のロサンゼルスオリンピックの時、大会前に1人でこの大学を訪問し、ちょうど大スタジアムで行なわれたオリンピック代表選考会でアメリカの選手の状況を視察していた事はのちに知った事でした。
父は自らを国際人でなく、「世界人」と決めて国籍には全くこだわらず亡くなるまで40以上の国で陸上競技のコーチをやっています。
父が残した国際スポーツにかかわる膨大な資料は、恐らく競技会開催国にも残っていないだろうと思われる貴重なもので、後世のかたのお役に立つものであることを願ってやみません。