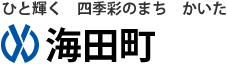海田町(カイタチョウ)名誉町民 織田 幹雄(オダ ミキオ)氏をたどる
第7回 選手からコーチ、監督へ
初めてコーチとして指導したのは、全国各地10カ所で開催された講習会であり、参加者は選手時代の1923年の極東大会で活躍した選手たちでした。それから70年の間(アイダ)、織田(オダ)さんは指導者として活躍しました。今回は、織田 幹雄(オダ ミキオ)さんの体験したこと、学習したこと、自覚したことが、いかに指導に繋がったのかを辿っていきます。
自分で自分を指導する
織田(オダ)さんは1924年のオリンピック パリ大会参加以降、大会に出るときには決まって、一番強い選手、世界一だと思う選手と練習しました。そうすることで、どこで自分が負けるのか、どこを間違っているのかを全部見ることができ、また、世界一の人と親しくなることができると考えていました。
また、緊張したら筋肉が硬くなって力が出ない、リラックスすることで集中できると考えており、「リラックス・集中力の指導は難しい。選手自身が体験的に覚えていかないといけない」と述べています。
あがることがなくなった心の工夫
負けず嫌いでどんなことも人に負けたくなかった織田(オダ)さん。人より多く練習をして、負けるという気持ちを持たないようにして競技に立ち向かいました。そして、相手を見て、どうしたら勝てるだろうかと工夫をこらして競技をすることで、あがることがなくなったそうです。織田(オダ)さんは、本の鵜呑み、外国選手のまね、コーチの言いなりではなく自分に適する方法・型を考え作り出すことが大事であり、自分なりの経験によってあがらなくなったと言っていました。織田(オダ)さん自身も、手の振り、足の動かし方を練習することで、自分なりの技術を身につけ、日本記録を達成することができました。この経験が選手への指導にも繋がっていたのではないでしょうか。
やる気を育てるのがコーチのしごと
織田(オダ)さんは、心が向かなければ、いくら技術的に強くてもだめであると言っていました。選手の時代から心の指導をする人だったのでしょう。世界の全ての競技選手と自分自身を育てるコーチであった、そんな印象を受けました。