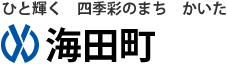俵尚子さん
海田町(カイタチョウ)民生委員児童委員協議会会長
プロフィール
たわら・なおこ
海田町(カイタチョウ)民生委員児童委員協議会会長、広島県民生委員児童委員協議会副会長。民生委員・児童委員として高齢者や障がい者、児童、母子世帯など要援護者の相談に応じ、行政や専門機関へのつなぎ役として社会福祉の向上に尽力する。「公平・公正」「人権への配慮」などを常に心掛けた活動を行う。
地域に根付き多彩に活動 民生委員・児童委員を22年
生まれも育ちも海田町(カイタチョウ)の私は、現在担当している新町地区で長くお世話になってきました。ある時、民生委員・児童委員をされていた前任者の方がうちを訪ねて来られ、「次の委員をぜひあなたに引き受けてほしい」とのお声掛けがありました。「私に務まるのかしら」と思いつつも、「何かお役に立てるなら」とお引き受けすることにしました。あれから約22年の月日が経ち、今では海田町(カイタチョウ)民生委員児童委員協議会の会長を務めるのと同時に、広島県民生委員児童委員協議会の副会長を兼任させていただいております。思えば、かつては統計調査員として活動したり、日本レクリエーション協会に所属し、インストラクターとして地域交流の場に関わってきたことも、地元をよく知ることにつながったような気がします。レクリエーション協会では、コーディネーターの資格を取得し、子どもをはじめとする地元の人たちが集うイベントの企画や、運営にも携わるようになりました。さまざまな場所で、より多くの人とつながれたことが、民生委員・児童委員として活動する上で非常に役立っていると感じています。
信頼関係を築き協力し合える体制を
先日、県の協議会から「新任研修で今までの経験をお話ししてください」と依頼を受けました。過去を振り返るにあたり、22年の間には本当に色々なことがあったとしみじみ感じています。私たちは、活動を行う上で気をつけなければいけないことが多々あり、見守りや相談支援の際にも、個人の生活に立ち入りすぎることがないよう活動するのもその一つです。例えば、ある日、地域の高齢者のようすが普段と違ったようで、近隣住民から「見に行ってほしい」と連絡をいただきました。急いで関係者の人たちと一緒に向かったところ、室内で倒れておられたので、医療機関や身内のかたに連絡を取って対応しました。このようなときに、病院に付き添ったりしたこともありますが、委員はあくまでボランティアです。夜中まで対応し、自宅に戻る交通手段がなくなったり、何かしらのトラブルに巻き込まれてしまうようなことがあってはなりません。委員は自分自身が元気で落ち着いているからこそ、地域の人たちに寄り添うことができるのです。―人では対応が難しいことも、色々な人と信頼関係を築くことで、しっかりとした協力体制のもと対応ができるようになるのです。
子どもたちの健やかな成長を願って
児童委員としては、普段は登下校(トウゲコウ)の見守りを主におこなっています。毎日顔を合わせるので次第に覚えてもらえるようになり、色々と話しかけてくれるお子さんも増えました。登校時は学校に向かう途中のためあいさつを交わす程度ですが、下校時は、その日にあったことなどを話してくれたりもします。ある時、小学生が踏切の遮断機に傘をひっかけてしまい、それが取れなくなるという事態が発生しました。「おばちゃん、大変大変」と私のところに知らせに来てくれ、一緒に傘をはずして何とか事なきを得ました。「踏切の近くは事故が起きやすい危険な場所だからね」と、その時はしっかり話して聞かせ、そのまま帰宅を見守りました。後日、学校の先生から丁寧な連絡をいただき、学校側でも再度入念な指導をおこなったことと、感謝の言葉をいただきました。イタズラ心でやってしまったことかもしれません。だいじなのは、そこで「これは危険」とか「してはいけなかったこと」だと子どもたちが気づき、次に生かすことです。子どもたちが健やかに成長していけるよう、見守る大人の目がより多くあることはだいじだと思います。近年では新しいマンションも増え、実態が把握しづらいエリアもありますが、やはりある程度の地域や人のつながりは大切なのではないでしょうか。
皆で連携して課題を解決地域共生社会を実現したい
現在進めているのは、地域と地域の連携。熊野町、坂町の協議会とは横のつながりを展開し、三町合同での研究会を開いています。今年は海田町(カイタチョウでの開催ということで、2月には防災についての研修会を開き、約110人の参加がありました。参加した委員から「とても勉強になる会だった」「また開いてほしい」といった声もあり、ほっとしたのと同時に、非常にうれしく思いました。今後も、要支援者の避難行動など、災害時の個別計画を推し進めていきたいと考えています。また、コロナ禍でストップしていたブックスタートパックの訪問配布を再開します。これは生後5カ月ごろの赤ちゃんがいるお宅に、絵本のプレゼントを持って訪問するというかいた版ネウボラの取り組みの一環です。何か困りごとがないかなどを聞き、母子サポートをおこなっています。私たちは普段、担当エリアの家庭を訪れ、緊急連絡カードの記入をお願いしたり、相談事に乗るといった活動をしています。ぜひ活動にご協力いただき、皆で見守り合える地域づくりをしていければと思います。そして、人と人が助け合い、誰もがくらしやすく生きやすい地域共社会を実現したいと思っています。
MY Favorite 海田のお気に入り
心温まる手作り弁当交流会
民生委員児童委員協議会と社会福祉協議会は車の両輪となってたような活動をおこなっています。社協の活動で感銘を受けたのが、海田高校家政科の生徒さんが地域の高齢者に手作り弁当を振る舞ってくれる「手作り弁当交流会」。若い人たちと高齢者の温かな交流の場にとても感動しました。