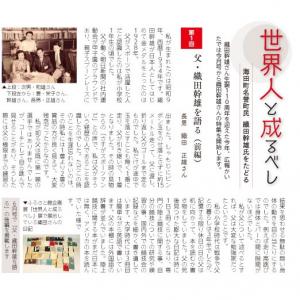織田幹雄さん
織田幹雄さんの生涯
幼少期
織田幹雄さんは、1905(明治38)年に広島県海田市町(現・安芸郡海田町)で生 まれました。身体は小さくても丈夫で、成績は優秀でした。学校から帰れば、近所の子どもたちと野山をかけまわっていました。
まれました。身体は小さくても丈夫で、成績は優秀でした。学校から帰れば、近所の子どもたちと野山をかけまわっていました。
この遊びを通じて、運動神経や強いバネが養われたそうです。人前でおしゃべりをしたり、何かやることは苦手な恥ずかしがりやさんでした。
織田さんは6人兄弟の3番目。家の手伝いは何でもやりました。井戸から水をくみ、風呂を焚く。他の手伝いも、工夫をこらしながら進めると、面白いようにはかどったそうです。
陸上競技との出会い
鼓浦尋常高等小学校(現・海田小学校)に通っていた織田さんは、両親に経済的な負担 をかけまいと、中学進学をあきらめかけていました。小学5年のとき、担任だった檜垣先生が父親を説得し、念願だった広島中(後の広島第一中学、現在の広島国泰寺高校)に進学します。中学1年のとき、あがり症の織田さんは、人前で跳躍がうまくできませんでした。体操の教官・宇佐美先生から1週間の補講を受けて練習を重ねたところ、クラスで一番高く跳べたそうです。織田さんは大いに褒められました。それからすっかり体が楽になり、人前でも平気で跳躍ができるようになったそうです。
をかけまいと、中学進学をあきらめかけていました。小学5年のとき、担任だった檜垣先生が父親を説得し、念願だった広島中(後の広島第一中学、現在の広島国泰寺高校)に進学します。中学1年のとき、あがり症の織田さんは、人前で跳躍がうまくできませんでした。体操の教官・宇佐美先生から1週間の補講を受けて練習を重ねたところ、クラスで一番高く跳べたそうです。織田さんは大いに褒められました。それからすっかり体が楽になり、人前でも平気で跳躍ができるようになったそうです。
織田さんの才能に気づいていた宇佐美先生は、アントワープオリンピックから帰った野口源三郎選手の講習会への参加を勧めました。その講習会で、織田さんは、陸上にいろいろな種目があることを学んだそうです。それまでは「陸上競技という言葉も知らなかった」と振り返っています。講習会の中で行われた記録会(走高跳)で、身長155cmの織田さんは、157cmのバーを越えました。(記録については諸説あり)「小さいのによく跳ぶな。君は練習すればきっと日本の代表になれるぞ。」織田さんは、野口選手にこう声をかけられました。この一言が後の跳躍人生のきっかけとなりました。
そのころ、サッカー部に所属していた織田さんは、新設された「徒歩部」へ入部します。織田さんは、サッカー部以外は許されていなかった全国大会への参加を校長先生に直訴します。「きっと優勝します」そう言った織田さんに校長先生は身銭を切って遠征を許可します。夏休みの40日間、校長と交わした「優勝」という約束を胸に、練習を1日も休まず続けました。結果は見事総合優勝。織田さんは、運命的な出会いを重ね、さらに工夫しながら努力を続けます。そして、1923年(大正12)年に第6回極東大会(アジア大会の前身)の日本代表に選ばれます。
初めてのオリンピック出場
1924(大正13)年、跳躍種目ただ一人の日本代表として、第8回オリンピック・パリ大会へ出場します。パリまでの40日間の船旅では、甲板を走ったり、マットを敷いて跳躍したりして調整しました。現地では積極的に外国の選手と練習しました。大舞台でも、もうすっかりあがることもなく、結果は三段跳で日本陸上界として史上初の6位入賞。大会後、「記録と勝負は別物である。独特の雰囲気のオリンピックでは、自分の力を出し切れるかどうかが重要だ。次期オリンピックをめざし、記録を1m伸ばす目標を立てた」と振り返っています。
ところが、厳しい練習による怪我をきっかけに、スランプに悩まされます。「もう織田は駄目かもしれない」と限界説もささやかれました。そこで織田さんは試行錯誤を続け、海外の選手のものまねではなく、「跳ぶ」ということの基本に立ち返ります。「いつどこに力を入れるのか。効果的な体勢は、踏み切りは。」毎日毎日ノートに書き留めました。記録を集約すると、3度のジャンプの比率が、6:4:5のときに距離が一番伸びることがわかりました。苦心の末、「織田さんのジャンプ」が完成します。
日本人初のオリンピック金メダル獲得
 迎えた1928(昭和3)年8月2日、第9回オリンピック・アムステルダム大会三段跳で、15m21cmの記録で優勝。織田さんは、日本人初のオリンピック金メダリストとなりました。国旗掲揚台のセンターポールには、手違いにより外国のものの4倍ほど大きな日本の国旗が掲げられました。織田さんは、「自分がそこまでやれたのはやはり努力だった。人は主体性をもった努力・工夫が大事だ。それは人それぞれなりにやればできる。」と振り返っています。郷里・海田では、母校、海田尋常高等小学校グラウンドで、歓迎会(祝勝会)が開催されました。「多くの人の力があったからこそオリンピックで優勝者にもなれた。」と、心の中が満たされる思いであったそうです。
迎えた1928(昭和3)年8月2日、第9回オリンピック・アムステルダム大会三段跳で、15m21cmの記録で優勝。織田さんは、日本人初のオリンピック金メダリストとなりました。国旗掲揚台のセンターポールには、手違いにより外国のものの4倍ほど大きな日本の国旗が掲げられました。織田さんは、「自分がそこまでやれたのはやはり努力だった。人は主体性をもった努力・工夫が大事だ。それは人それぞれなりにやればできる。」と振り返っています。郷里・海田では、母校、海田尋常高等小学校グラウンドで、歓迎会(祝勝会)が開催されました。「多くの人の力があったからこそオリンピックで優勝者にもなれた。」と、心の中が満たされる思いであったそうです。
戦後のスポーツ復興
大学卒業後、大阪朝日新聞社に入社。世界一のスポーツ記者をめざ しながら、三段跳でも15m58cmの世界記録を出します。その後、第10回オリンピック・ロサンゼルス大会の後に第一線を引退しました。戦後の日本にとって、オリンピック金メダリスト・織田幹雄の存在はとても大きなものでした。パリ大会で顔見知りとなったGHQの体育スポーツ監督官ニューフェルドから欧米のスポーツ視察を勧められ、各国を巡り、最新の理論を学ぶとともに、世界中の選手の指導にあたりました。織田さんの世界各国での貢献が第18回オリンピック・東京大会の開催につながりました。旧国立競技場のこけら落としとして開催された東京アジア競技大会では、最終聖火ランナーを務め、同競技場の第4コーナー付近には、織田さんが金メダルを獲得したときの記録15m21cmと同じ高さの、通称「織田ポール」が建てられました。東京オリンピックでは、陸上日本代表チームの総監督を務めました。
しながら、三段跳でも15m58cmの世界記録を出します。その後、第10回オリンピック・ロサンゼルス大会の後に第一線を引退しました。戦後の日本にとって、オリンピック金メダリスト・織田幹雄の存在はとても大きなものでした。パリ大会で顔見知りとなったGHQの体育スポーツ監督官ニューフェルドから欧米のスポーツ視察を勧められ、各国を巡り、最新の理論を学ぶとともに、世界中の選手の指導にあたりました。織田さんの世界各国での貢献が第18回オリンピック・東京大会の開催につながりました。旧国立競技場のこけら落としとして開催された東京アジア競技大会では、最終聖火ランナーを務め、同競技場の第4コーナー付近には、織田さんが金メダルを獲得したときの記録15m21cmと同じ高さの、通称「織田ポール」が建てられました。東京オリンピックでは、陸上日本代表チームの総監督を務めました。
数々の功績が認められ、1976(昭和51)年、IOC(国際オリンピック委員会)から「オリンピック功労賞」を授与されました。織田さんは、「競技力の向上」を追及する一方で、高齢者のスポーツ「マスターズ」の普及などにも尽力しました。「喜びのないスポーツ、楽しみのないスポーツは本当の意味でのスポーツではない」と、国民の誰もがスポーツを楽しむ社会の発展を願っていました。最後まで陸上競技の発展に尽力し、1998(平成10)年、神奈川県において93年の生涯を閉じました。
織田幹雄さんの展示などをしています
海田町ふるさと館
2階企画展示室3で、金メダル、スパイク、ディプロマ(オリンピックの賞状)などの競技にまつわる資料のレプリカ、小学生時代の賞状のレプリカ、幼少期から晩年までの写真などを展示しています。映像で織田幹雄さんについて学ぶこともできます。
海田総合公園
多目的広場横の芝生地に「織田幹雄氏 顕彰モニュメント」を設置していま
また、モニュメントの隣には、織田さんが金メダルを獲得した時の記録「15m21cm」を表示した体感ゾーンを整備しています。芝生地ですので、実際に飛んで記録の偉大さを体感することができます。
織田ポール(海田町内)
 織田幹雄さんがアムステルダムオリンピック三段跳で金メダルを獲得したときの記録と同じ高さ(15m21cm)の掲揚ポールを設置しています。設置している場所は、海田小学校、海田東小学校、海田西小学校、海田総合公園野球場です。
織田幹雄さんがアムステルダムオリンピック三段跳で金メダルを獲得したときの記録と同じ高さ(15m21cm)の掲揚ポールを設置しています。設置している場所は、海田小学校、海田東小学校、海田西小学校、海田総合公園野球場です。
織田幹雄さんの特集をしました
広報かいた平成27年5月号から平成28年4月号において、織田幹雄さんの特集を掲載しました。